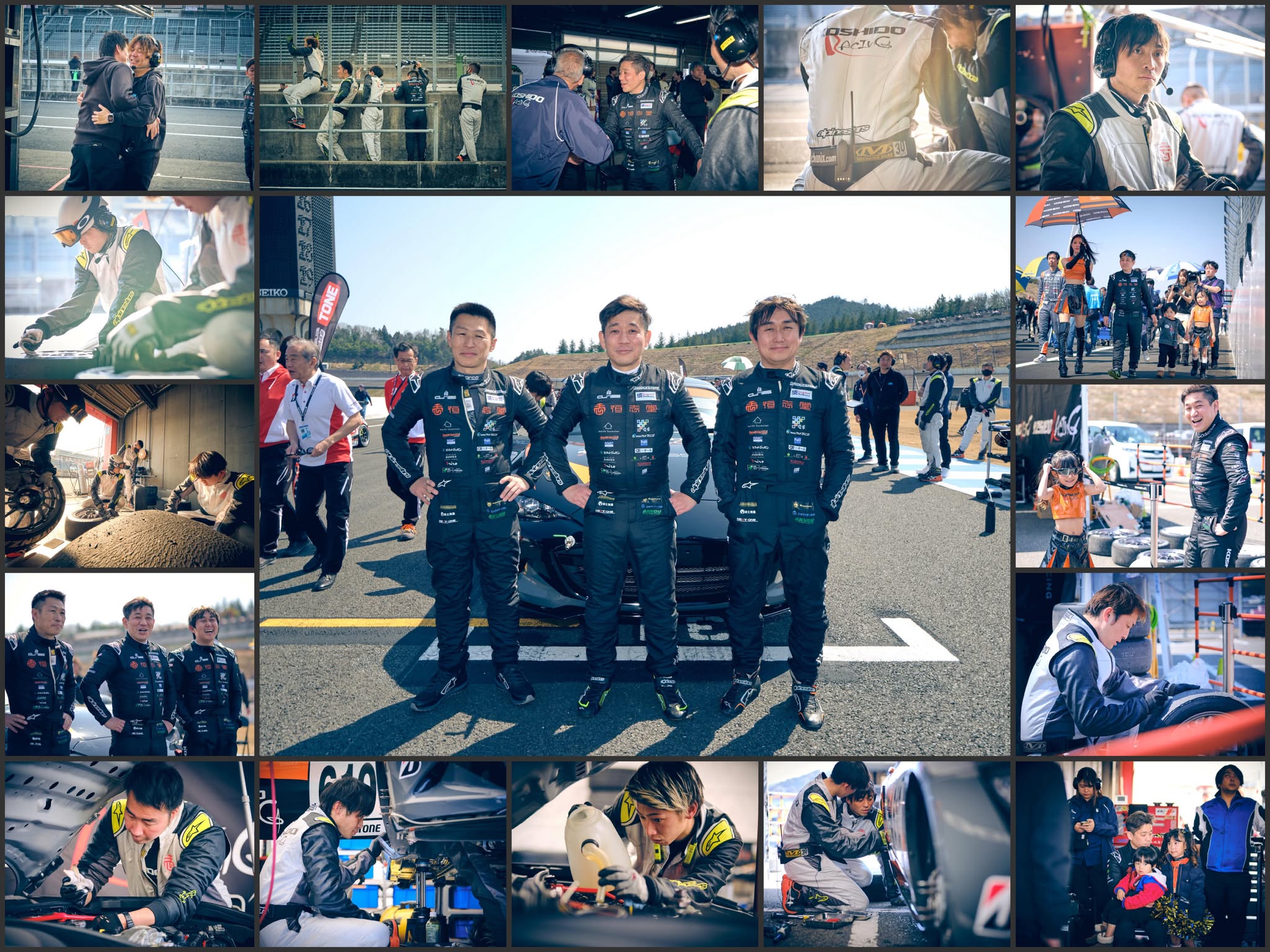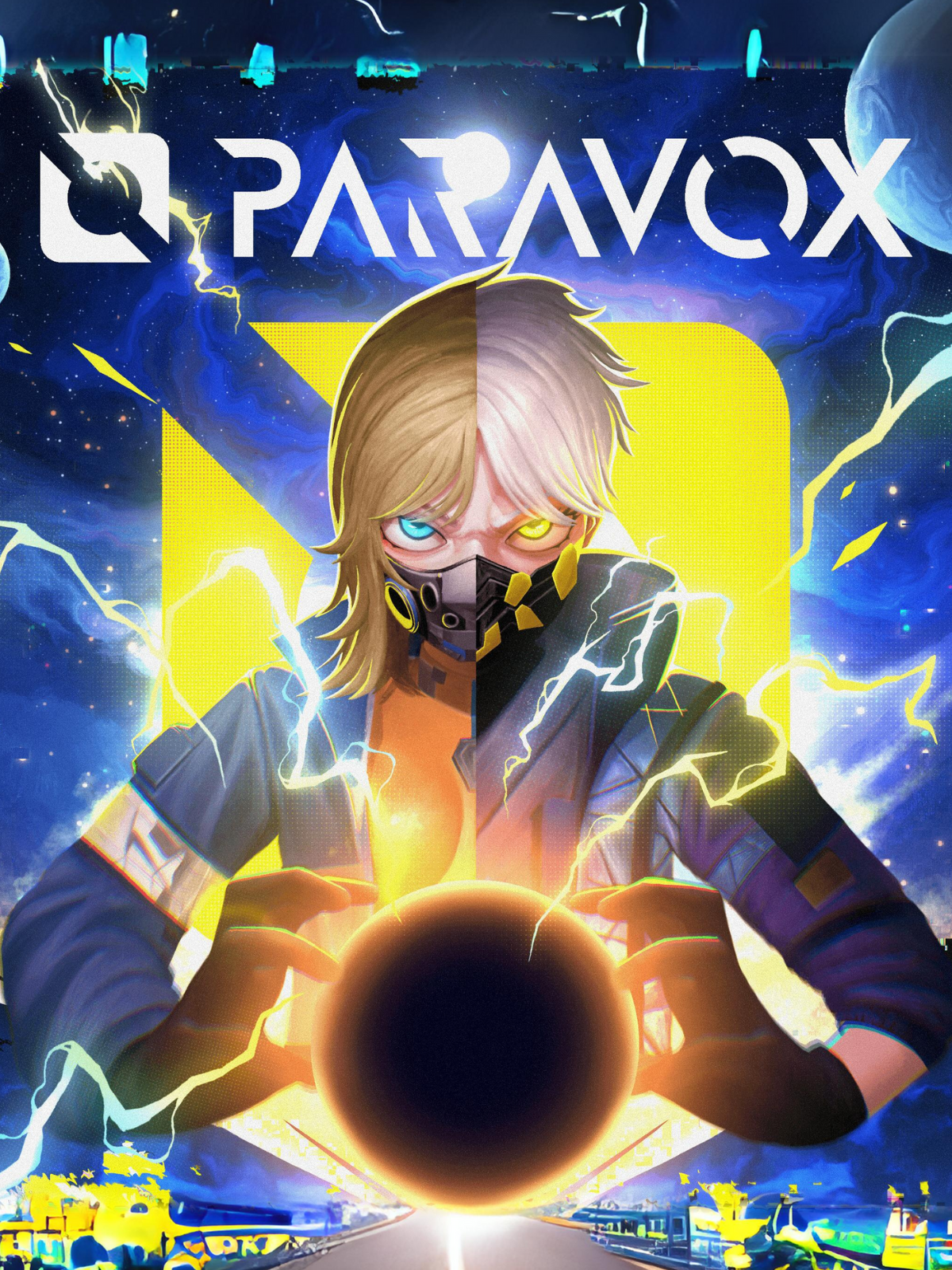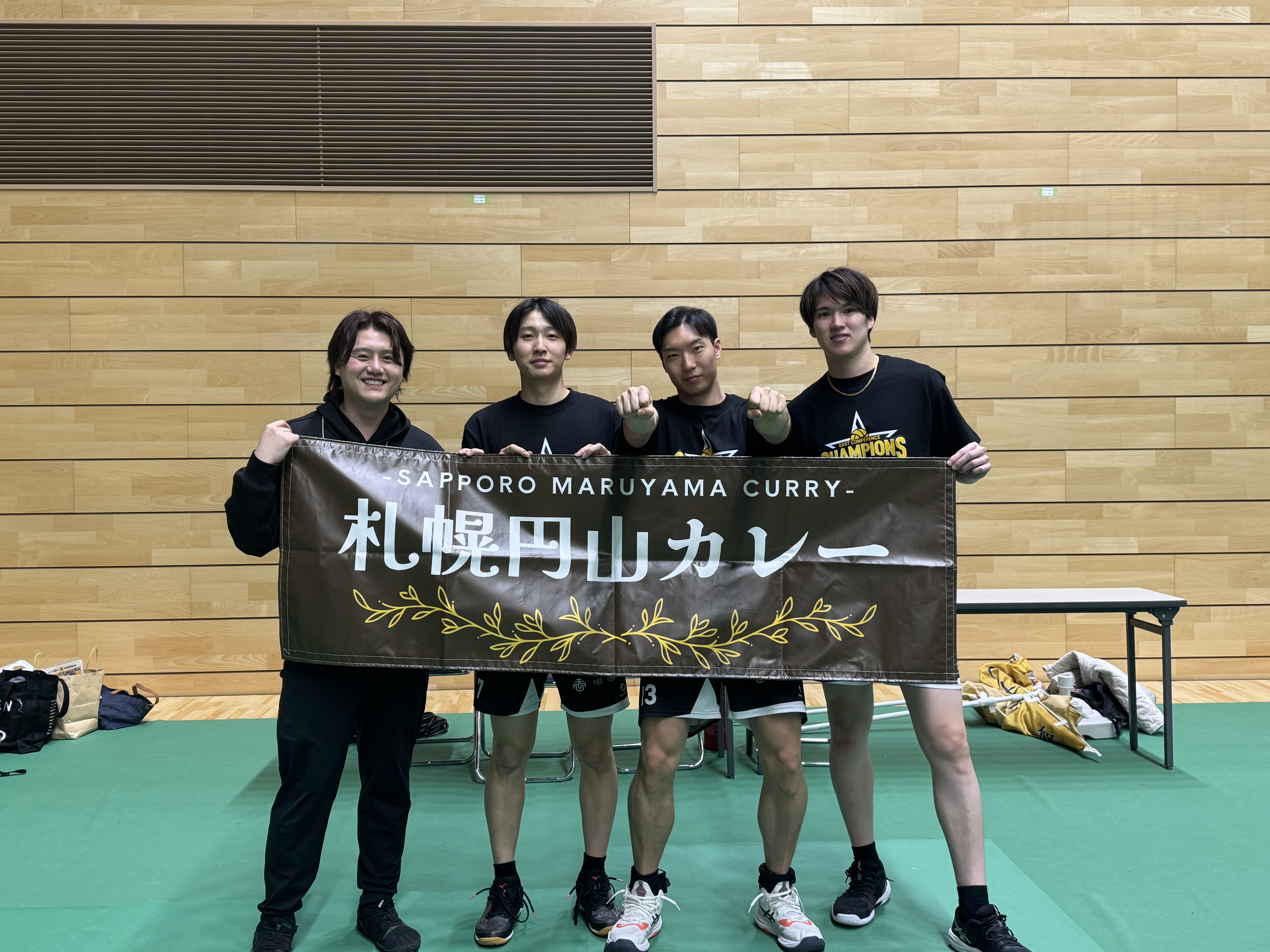2025.04.07 【物件紹介】カレラ二十四軒で、ちょっといい暮らし始めませんか?
みなさん、こんにちは!企画開発部、新入社員の藤井です!
今日は、札幌市西区二十四軒の物件をご紹介します✨
その名も――
「カレラ二十四軒」

「カレラって、あの高級車の名前みたいでカッコよくない?」
そんな軽い気持ちで内覧に来たあなた、きっと帰るころには本気で住みたくなっていることでしょう。
🚇 アクセス抜群!駅チカがうれしい
地下鉄東西線「琴似駅」徒歩4分
JR函館本線「琴似駅」徒歩12分
雨の日も、雪の日も、外出が苦にならない距離感。
冬の札幌でこの駅近さは、もはや反則級です。
🏡 設備が充実しすぎて、ちょっとドヤ顔したくなるレベル
・都市ガス(経済的!)
・宅配ボックス(不在でも荷物OK!)
・オートロック(セキュリティ安心)
・屋内駐輪場
・24時間換気(いつでもフレッシュ)
・エアコン(夏も余裕)
・TVモニターフォン(誰が来たかバッチリ)
・温水洗浄便座
もう、「あれがない!」なんて文句は言わせません。
🛋️ お部屋の中もぬかりなし
■ リビング
広々リビング+木目調の床で、
なんだか自然と深呼吸したくなる空間に。
アクセントクロスの爽やかカラーが、あなたの毎日をこっそり元気にしてくれます🌿

■ キッチン
天板には人造大理石を使用。
高級感も、キズや汚れへの耐性もバッチリ。
料理中に「私ってもしかして料理上手…?」って錯覚しちゃうかも。

■ ウォークインクローゼット
「服、しまう場所足りない問題」に終止符を。
バッグや帽子、アクセサリーまで余裕でしまえて、毎朝のコーディネートがはかどること間違いなしです。

■ UTスペース
広々&シャンプードレッサー付き。
朝の身支度タイムが、優雅なひとときに変わります。
(バタバタ支度していた過去の自分にバイバイしましょう👋)

🐾 まとめ:カレラ二十四軒は、”ちょうどいい贅沢”がそろってる
駅近、オシャレ、充実設備。
これだけ揃ってたら、もう迷う理由がないですよね?
お問合せ先
MAIL:[email protected]
TEL:011-530-0010
FAX:011-351-2170
株式会社スペチアーレ コウシドウ不動産
住所:札幌市中央区南19条西14丁目2-35 スペチアーレ伏見1F